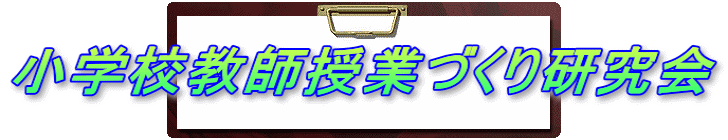
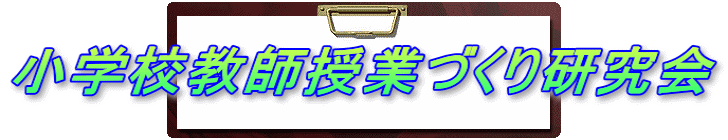
平成26年度からの新情報は次のボタンをクリックしてください。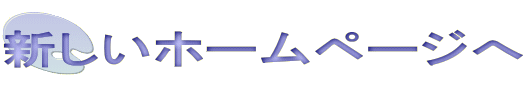 |
| 1.本研究会の趣旨 小学校教師は、自分の教室にいる子どもたちの一人一人を育てることが「仕事」である。 ある学校の3年生の教室。毎日毎日、朝早くに登校してくる子どもたちに、国語・社会・算数・理科・音楽・体育・図工・道徳・総合の授業を通して、人として「生きる力」(学力)を育むために、教師としての持てる力と思いを注ぎ続ける。すなわち、「小学校教師」であることは、全教科・領域の確かな「授業力」が求められるということ。 ただ、小学校教師は、万能ではない。得意・不得意の教科が当たり前だが、ある。 けれども、子どもたちには、すべての教科・領域における学力を獲得する権利をもつ。だからこそ、私たち教師は、学ばなければならないだろう。この教科で育むべき学力とは何か。そして、どのような授業をつくっていけばいいのか。 本校、筑波大学附属小は、研究校として、教科専科制を採っている。例えば、3年生は、基本的には、各教科・領域「国語・社会・算数・理科・音楽・体育・図工・道徳・英語」すべての授業をその専科の先生方が担当する。1人の子どもを、9人の先生方が育てているのだ。 専門教科の授業研究を責務としている本校の私たち教師は、公立現場の全教科・領域を担当している先生の大変さは知らない。しかし、専門教科の授業づくりについては多くの研修を重ねてきた自負を持っている。公立現場の先生方の研修のために、本校教師の私たちが寄与できることはきっと大きいと信ずる。本研究会の意義はここに、まずある。 本会のもう一つの大きな特色は、授業づくりの対象学年を毎回限定することにある。 一昨年の第1回大会は1年生の授業づくり。昨年の第2回大会は2年生の授業づくり。 その提案授業はそれぞれの対象学年の子どもたちの学び、講座もその学年段階を意識した。 2年前に本会を旗揚げした中心メンバーの4人は、当時、1年生4クラス160人の担任団。偶然にも、国語・社会・算数・理科の4教科の教師が揃った。基本的には、この4人は、今後、学年が上がっても、担任団として160人を育てていく仲間となる。 さらに、この4教科以外の教科・領域で、同じ1年生の子どもたちの授業を担当する教師仲間がメンバーに加わり、この研究会をともに進めていくことになった。 この会を毎年続けていくことは、1年生7歳の子どもたちが、すべての教科・領域の授業を通し、いかに成長していくかを、時の流れの中で確かに見取ることに他ならない。 あんなに幼かった未熟な1年生7才たちが、12才6年生となり、賢く、優しく、たくましき姿を見せてくれる日。それは、私たち小学校教師の願いであり、いきがいであり、楽しみ。そんな思いのもとで、この「『小学校教師』授業づくり研究会」を設立した。 |
|
2.研究会メンバー |
|
|
|
2013年7月21日(平成25年)「3年・低学年と中学年の接続期の指導」 ◆授業講座 算数(盛山)・理科(鷲見) ◆ワークショップ講座 ・図工(仲嶺) ・道徳(加藤) ・英語(荒井) ・社会(梅澤) ・体育(眞栄里)・音楽(平野) ◆講演 国語(二瓶) ○第4回「小学校教師」授業づくり研究会 2014年(平成26年)1月18日「中学年の学びを育てる」 ◆授業講座 国語(二瓶)・社会(梅澤) ◆ワークショップ講座 算数(盛山)・理科(鷲見)・音楽(中島)・図工(西村) 体育(眞栄里)・道徳(加藤)・英語(荒井) |
| 本研究会への問い合わせ先 shougakujugyou123456★yahoo.co.jp (★を@に変えてください) |